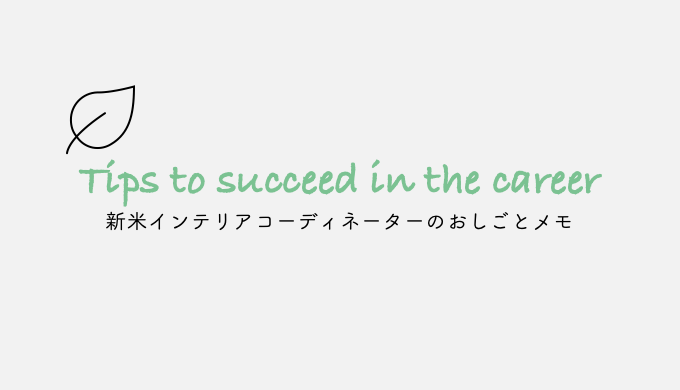インテリアコーディネーターであることを名乗ると「インテリアは感性の仕事」「インテリアコーディネーターはセンスがいい」とよく言われます。また「あなたは感性が豊かだからインテリアの仕事に向いている」と言われてインテリアの仕事に興味を持った方も多いでしょう。
しかし、一方で実際に仕事に就くと「自分にはインテリアセンスがないのでは・・」と不安に思っている新米インテリアコーディネーターも多く、一体どうしたらセンスが身につくんだろう、自分のセンスに自信がない、と悩んでいる人も少なくありません。
このページでは、今日から実践できるインテリアセンスの磨き方についてご紹介します。
実際に新人教育の場でも取り入れた具体的な学び方で、受講後に多く「有効な勉強だった」「これ使って勉強します」と感想をいただいた内容です。
インテリアセンスに自信のない方でもこの方法ならば、誰でも簡単に着実にステップアップができますよ。
それではセンスの世界へようこそ。
 江戸小紋空間デザイン
江戸小紋空間デザイン